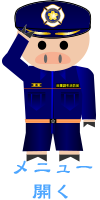防災豆知識
地震がきたら・・・。
地震のメカニズムについて
地震には「海溝型地震」と「直下型地震」の2タイプあります。
・海溝型地震・・・
地震の多くは地球の地表をおおっているいくつかのプレート(地殻)の運動によって起こります。日本に地震が多いのも、日本列島が複数のプレートが重なり合う場所にあるからと見られています。
地球の表面はいくつかのプレート(地殻)でおおわれ、マントルの対流とともに年間数㎝の速度で動いています。
そのため、プレートのぶつかり合うところに歪みが生じます。
この歪みが限界に達すると、引きずり込まれたプレートが元に戻ろうとして跳ね返り地震を起こします。
プレートの境目で地震が多い理由もここにあります。
1993年7月に発生した北海道南西沖地震も、ちょうどユーラシアプレートと北米プレートの境目で起こっています。
また、1923年に発生した関東大震災や、現在心配されている”東海地震”もこのタイプによるものです。
・直下型地震・・・
内陸部でプレートそのものや地殻の内部がひずみ、部分的に壊れそうになる場所ができます。
そのひずみが限界に達した時、ひびが入るように壊れて断層になります。
この現象が起きたときが直下型の地震です。
1995年に発生した阪神淡路大震災がこのタイプによるものです。
マグニチュードと震度とは・・・
マグニチュードとは地震そのものの規模のこと。震度はそれぞれの場所での揺れの強さを表し、震源からの距離や地盤の状態などによって異なってきます。一般にはマグニチュードが大きくても震源から離れていれば震度は小さくなります。
| 震度 | 人間への影響 | 屋内の状況 | 屋外の状況 |
|---|---|---|---|
| 0 | 揺れを感じない | 変化なし | 変化なし |
| 1 | 屋内の一部の人が僅かな揺れを感じる | 変化なし | 変化なし |
| 2 | 屋内の多くの人が揺れを感じる、寝ている人の一部が目を覚ます | 電灯などのつりものが僅かに揺れる | 変化なし |
| 3 | 内のほとんどの人が揺れを感じる、恐怖感を感じる人も | 棚の食器類が音をたてることも | 電線が少し揺れる |
| 4 | かなりの恐怖感、寝ている人のほとんどが目を覚ます | つりものが大きく揺れ、食器類は音を立て、置物が倒れることも | 電線が大揺れ、歩行者が揺れを感じ、揺れを感じる運転者も |
| 5(弱) | 多くの人が身の安全を図ろうとする | 電線が大揺れ、歩行者が揺れを感じ、揺れを感じる運転者も | 窓ガラスが割れ落ち、電柱の揺れがわかる、ブロック塀が倒れたり、道路に被害も |
| 5(強) | 非常な恐怖、多くの人の行動に支障 | 食器類、本の多くが落ち、テレビが落ちたり、タンスが倒れることも | 補強のないブロック塀の多くは崩れ、自販機や墓石が倒れることも、車の運転は困難に |
| 6(弱) | 立つのが困難 | 未固定の重い家具の多くが移動転倒、開かないドア多し | 補強されていないほとんどのブロック塀が壊れる |
| 6(強) | 這わないと動けない | 未固定の重い家具のほとんどが転倒、戸がはずれる | 補強されていないほとんどのブロック塀が壊れる |
| 7 | 自分の意志で動けない | ほとんどの家具が大きく移動、飛ぶことも | 補強のあるブロック塀の破損も |
地震の時の3大心得
1・身の安全を守る
大きな揺れが続くのはせいぜい1分ぐらい。
転倒のおそれがある家具からすみやかに離れ、テーブル、机、ベット、布団などの下にもぐる。
その際、座布団、クッション、枕などで頭の保護を。
身近に何もない場合は手で頭を覆う (手のひらは下向きに)
2・脱出口を確保する
揺れが激しいとドアや窓が変形して開かなくなり、室内に閉じこめられることがある。
揺れの間合いを見てドアや窓を開け、あらかじめ逃げ口をつくっておく。
とくに入り口が少ないマンションや団地の場合は忘れずに。
3・火の始末をする
小さな揺れの場合は、ただちに火の始末をする。
ただし、規模の大きな地 震の時は、やけどなどをさけるため揺れがおさまってから火の始末を。
ガスは元栓を閉め、電気器具はスイッチだけでなくコンセントも抜いておく。
地震に対する日常の備え
大地震が発生した時に、落ちついて行動できるよう、次のことを普段から心がけ、いざというときに迅速に行動できるようにしましょう。
1・家族での防災会議
大規模地震のとき、家族があわてずに行動できるように、普段から次のようなことを話し合い、それぞれの分担を決めておきましょう。
・家の中でどこが一番安全か
・救急医療品や火気などの点検
・幼児や老人の避難は誰が責任を持つか
・避難場所、避難路はどこにあるのか
・避難する時、誰が何を持ち出すか、非常持ち出し袋には何を入れ、どこに置くか
・家族間の連絡方法と最終的に確認し合う場所はどこにするのか
・昼の場合、夜の場合の違いをどうするか
また、家族が会社、学校買い物など別々の場所で地震にあった場合の連絡方法や最終的な避難場所も決めておき、これらを記入した避難カードを作成し、各自携帯しましょう。
2・非常持出品の準備
避難場所での生活に最低限必要な物を準備し、また、負傷したときに応急手当ができるように、応急手当ができるように、応急医療品などもリュックサックや非常持出袋に入れて、いつでも持ち出せる場所に備えておきましょう。
(非常持ち出し品の一例)
・印鑑
・
貯金通帳
・懐中電灯
・ロウソク
・手袋
・水
・携帯ラジオ
・現金
・ライター
・ナイフ
・ミルク
・哺乳びん
・紙おむつ
・インスタントラーメン
・食品
・缶切り
・救急箱
・衣類
・毛布
・ヘルメット
・防災ずきんなど
非常持ち出し袋は、目安として男性で15㎏以下、女性で10㎏以下にまとめるのが良いとされています。
3・消火器などの備え
万が一の出火に備えて、消火器や消火用三角バケツなどをすぐに使える場所に用意したり、風呂の水はいつもためておくように心がけましょう。
また、火災が発生したときに確実に消火できるように、普段から防災訓練などに参加し、消火器の使い方になれておきましょう。
夜間の避難のための懐中電灯、床に飛散したガラスによるけがなどを防ぐために厚手のスリッパや運動靴を用意しておくのも良いでしょう。
地震 そのときの10のポイント
・グラッときたら身の安全
・すばやい消火、火の始末
・窓や戸を開け、出口を確保
・落下物、あわてて外に飛び出さない
・室内のガラスの破片に気を付ける
・協力しあって救出・救護
・門や塀には近寄らない
・確かめ合おう、我が家の安全、隣の安否
・避難の前に安全確認、電気・ガス
・正しい情報、確かな行動